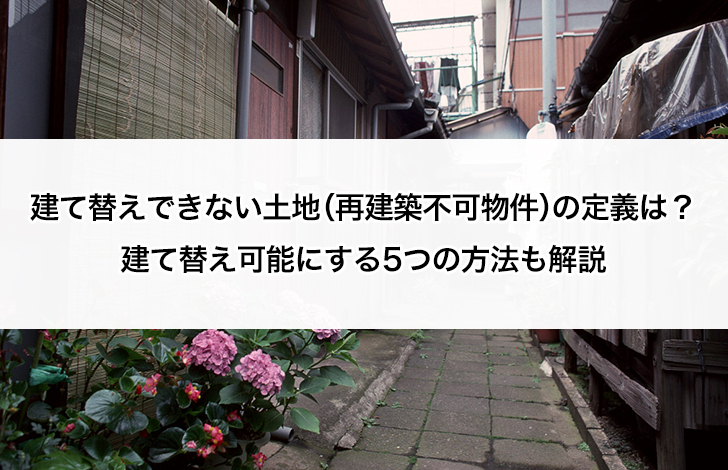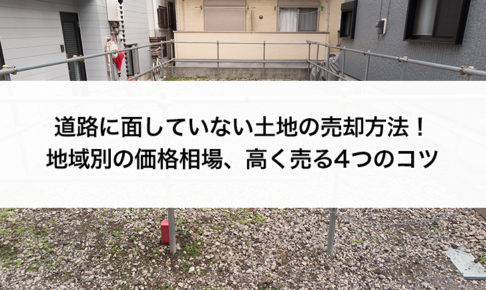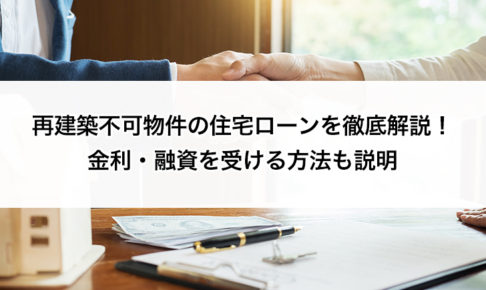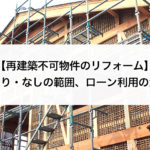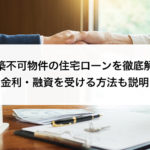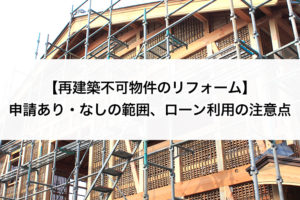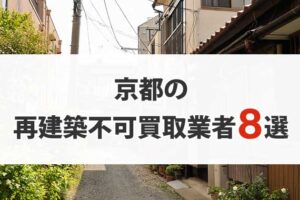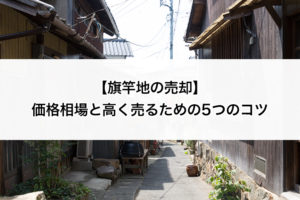建て替えできない土地は、土地の状況や周辺環境が原因で、住宅の再建築が制限されている土地のことです。
日本全国どこでも存在している土地なので「相続した土地が建て替えできない土地だった」「購入しようとした家が再建築不可物件だった」という方も少なくありません。
建て替えのできない土地を相続・売買する方の中には、
- 建て替えできない土地の定義は?
- 建て替え可能にする方法はないのか?
- リフォームはどこまで可能なのか?
など疑問に思われている方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は建て替えできない土地の条件、建て替えできる方法、リフォームの可能範囲について詳しく解説します。
目次
建て替えできない土地とは

建て替えできない土地とは、建築基準法(建築物における日本の法律)で、接道義務を果たしていない土地のことです。土地ではなく建物の場合は「再建築不可物件」と呼ばれています。
接道義務を果たしていない再建築不可物件のこと
接道義務は、建築基準法に定められている住宅地に課せられるルールの一つ。緊急車両の進入や災害時の避難の観点から、一定以上の広さの道に接することを義務付けています。違反していると街の安全を確保できないため、義務を満たせるよう工事するまでは再建築が禁止されています。
接道義務違反の土地とは
接道義務を満たすには、原則として敷地が2メートル以上道路に接していなければならず、この基準を満たしていないものが接道義務違反の土地となります。
接道義務を満たせる「道路」は何でもいいわけではなく、その内容が建築基準法に記載されています。接道義務を果たせる道路の定義は、以下の記事で詳しく説明しています。
接道義務違反の土地はいくつか種類がありますが、不動産広告などでよく見かけるのは以下の二種類です。
- 袋地
- 旗竿地
袋地は他人の土地に囲まれており、旗竿地は敷地から道路まで路地が飛び出しています。かなり独特の立地や形状をしているので判別しやすいです。土地を相続・売買する際は、再建築可能かどうか注意深く確認してみてください。
袋地・囲繞地
袋地は、他人の土地に取り囲まれ、道路と隔てられている土地のことです。これに対して、袋地を取り囲んでいる土地を指して囲繞地(いにょうち)と言います。
袋地の住人は、道路から自宅に出入りする際、必ず他人の土地のどこかを通行することになります。車の乗り入れなども難しく、接道義務違反の土地の中でも特に敬遠される傾向の強い土地です。
旗竿地
旗竿地は、道路に向かって土地から細長い路地が伸びているような形状の土地です。道路に旗が立っているように見えるため、旗竿地と言われています。
接道はしていても、その道が建築基準法上の道路ではない場合や、道路と接している路地の幅が2m未満の場合、接道義務違反の土地となります。
建て替えできない土地を「建て替え可能」にする5つの方法

再建築不可でも、建て替えを制限されている理由を取り除くことで、建て替え可能にできるケースがあります。全ての土地に対して有効ではありませんが、その方法を5つご紹介します。
隣の土地と合筆する
隣接した二つの土地を一つの土地として登記することを合筆と言います。隣の土地が接道義務を満たしている場合、その土地を買い取って合筆すれば、もともと再建築不可の土地も再建築できるようになります。
隣地の所有者が土地の売却を計画しており、かつ買い主の資金に余裕がある場合に限りますが、再建築できるようにする方法としてはもっともシンプルなものです。
通常、土地の売買は仲介業者に依頼して行われることが多いです。売買契約には以下の準備が必要となります。
売り主側
- 売買契約書
- 身分証明書
- 実印・印鑑証明書
- 住民票
- 建築確認済証および検査済証、建築設計図書・工事記録書等
- 土地測量図・境界確認書
- 固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書
- 登記済権利書または登記識別情報
買い主側
- 住所証明書類(住民票)
- 写真付き身分証明書
- 実印・印鑑証明書
- 登録免許税(不動産の登録にかかる税金 対象不動産評価額の1000分の2)
各書類の準備は仲介業者に相談してからでも問題ありませんが、売買を急ぐ場合は事前に準備できるものを揃えておけば、手続きもスムーズに進めることができます。
隣地の一部を借りて接道義務を果たす
土地の買取が難しい場合は、隣地の一部を借りることもできます。隣地を丸ごと売買する場合と違い、貸借契約は両者の合意によって解除することができます。借りる土地も接道義務を満たす分だけなので、隣地所有者の負担や心理的ハードルも低いです。
貸借契約を結ぶ場合、必要書類は以下の4種類となります。
- 賃貸借契約書
- 身分証明書
- 実印・印鑑証明書
- 土地の登記簿謄本
こちらも、仲介業者や司法書士などの専門家に依頼するのが安心ですが、自分で手続きすることも可能です。交渉がスムーズに進んだ場合、話し合いから契約締結まで最短一週間ほどとなります。
土地の一部に位置指定道路としての認定を受ける
位置指定道路は、建築基準法42条第1項第5号に規定されている私道の一種です。敷地の一部を道路として工事することで、市区町村の建築担当課から認定を受けて接道義務違反の状態を解消できます。
建築基準法に定められている位置指定道路の基準は、以下の通りです。
- 道幅が4メートル以上になるようにし、道路との接続部に隅切りを設置する
- 道路の形態とその境界が明確であり、排水設備があること
- 通り抜けが可能であること
- 行き止まり道路の場合、長さが35メートル以下であること
参照:電子政府の総合窓口 e-GOV|建築基準法42条1項五号
隅切りは、右左折時の安全確保や進入時の衝突防止のために、道路の角を斜めに切り取り視界を確保することです。隅切りを行なった道路は入口がカクテルグラスのような形になります。
建築基準法の規定の他にも、自治体ごとに独自の運用基準が存在する場合があるため、位置指定道路の認定には申請前に市区町村の建築課への相談が必要です。便利な制度ですが、中古一戸建の土地としては大きな面積を負担しなければならず、敷地いっぱいに家が建っている場合は採用されないことが多いです。
43条但し書き道路の認定を受ける
43条但し書き道路とは、4メートル以下の幅員の道路に接している場合でも、一定の基準のもと例外的に再建築を認めるという建築基準法の規定です。
詳細は、建築基準法施行規則第10条の2に規定されており、以下のどれかに適合していなければなりません。
- 敷地の周囲に公園・緑地・広場等の広い空き地が存在すること
- 農道などの公共の道(幅員4メートル以上のものに限る)に2メートル以上接道すること
- 道路に通じており、避難・通行の安全が確保できる十分な幅を持つ道に有効に接すること
参照:電子政府の総合窓口 e-GOV|建築基準法43条
参照:電子政府の総合窓口 e-GOV|建築基準法施行規則第十条の二
以上の基準を満たし、建築審査会の許可が降りれば再建築が可能となります。
しかし、現在まで建築の許可が出ていない物件は、現実的には認定を受けるのは難しいと考えられます。43条但し書きは、ご紹介したように認定のための基準が厳しく、実質的には建築基準法上の道路と同レベルの環境が求められるためです。
また、時間の経過も理由の一つです。建築基準法が定められた昭和25年から、2019年現在で既に60年以上経過しています。許可の可能性のある土地なら、既に以前の持ち主が売却前に許可申請をおこなっていると考えられるためです。
現実的には認定は難しいですが、手段のひとつとして頭の片隅に留めておいてください。
セットバックする
セットバックとは、道路の幅を広げるため、接している土地の境界を後退させることです。
建築基準法の施行前に作られた幅4メートル未満の道は、行政から指定を受けた場合、建築基準法上の道路とみなす例外規定があります。このルールは建築基準法第42条2項に規定されているため、建築業界では「二項道路」と呼ばれています。
二項道路に面している住宅は、道幅が4メートルになるよう敷地をセットバックさせれば再建築が可能となります。
道路によって元の幅が異なるため、セットバックする面積はケースによって異なります。基準は以下の表の通りです。
| 道の状況 | セットバックする面積 |
|---|---|
| 道の反対側に家が建っている | 道の中心線から敷地までが2mになるように後退させる |
| 道の反対側が住宅ではない | 道の反対側から敷地の境界までが4mになるよう後退させる |
セットバックすると、所有していた敷地を道路として市区町村に提供することになります。敷地の面積が小さくなり財産評価も変動するため、セットバックを検討している場合は一度不動産会社に相談し、セットバックする前と後で、どの程度得をするのか、また損失が出るのか確認してみるといいでしょう。
再建築不可物件でもリフォームが可能

再建築不可物件を再建築可能にするには、手間や費用がかかることがお分かり頂けたと思います。ではリフォームの場合はどうでしょうか。
実は再建築不可の建物は、「再建築不可」と注意書きが付いていますが、修繕やリフォーム、リノベーションといった工事が可能です。
骨組みを残してフルリフォームできる
再建築不可物件は、屋根や柱といった骨組みを残してフルリフォームすることが可能です。
再建築不可物件が禁止されている内容は、リフォームではなく新規の建築と建て増しです。一度更地にして新しい建物を作ったり、既存の建築物を増築して延べ面積を増やしたりすることはできません。
骨組みと総面積はそのままにする必要があるため、建物の規模や内装、間取りにはある程度の制約はつきますが、ほぼ新築一戸建て同様の改築が可能です。
リフォームローンで資金の調達が可能
再建築不可物件の改築には、リフォームローンを利用して資金を調達することができます。
不動産でローンを組む場合、住宅ローンをイメージされる方が多いかと思いますが、再建築不可物件は土地の資産価値が低く、購入対象の物件を担保にする住宅ローンの利用は難しいです。その点リフォームローンは無担保で利用できるものが多く、担保にならない再建築不可物件にも使うことができます。
再建築不可物件のリフォームでのローン利用については、以下の記事で詳しく説明していますので参考にしてみてください。
再建築不可物件でも専門業者なら高く売れる
通常の不動産業者は、再建築不可物件の取り扱いには慣れていないことが多く、価値を正しく判断できない可能性があります。そのため需要の高い好立地の土地でも、再建築不可であることを理由に不当に安い売却価格を提示されることも考えられます。
一方、訳あり物件に特化した専門業者であれば、建て替えできない不動産であっても独自の販売ルートや運用ノウハウを保有しているため、高額での買取が期待できます。
売却を検討されている方は、普通の不動産業者と訳あり物件専門業者のどちらにも査定依頼をし、価格を比較してみてください。
まとめ
以上、建て替えできない土地の条件、建て替えできる方法、リフォームの可能範囲についてご紹介しました。
再建築不可物件は、そのままでは建て替えができないため、通常宅地と比較すると財産評価や相続税の評価も低いです。しかし、工夫次第では立て替えが可能の場合や、新築同様にリフォームすることで価値を高めることもできます。
また売却を検討されている方は、特殊物件の取り扱いが豊富な訳あり物件専門業者のほうが高額買取が期待できますが、普通の不動産業者と訳あり物件専門業者のどちらにも査定依頼をし、一度価格を比較してみるといいでしょう。